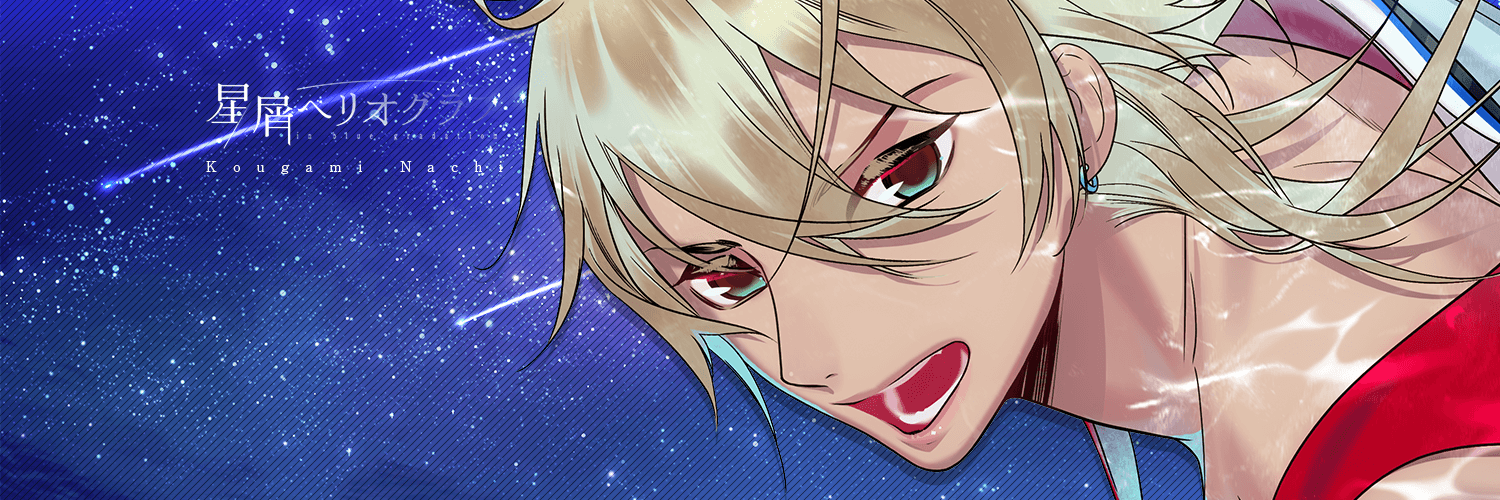夜空にはきらりと瞬く星がたくさん散りばめられている。
それを眺めながら今日あったことや、明日のことを考えたりして眠りについているはずなのに。
今日ばかりは空一面に雲がかかっていて星が見られない。代わりに星よりも明るい月が、雲のはざまからうっすらと顔を覗かせていた。
ベッドに横たわり、暗く重い気持ちを吐き出すようにため息を吐く。
このため息の原因は簡単だ。明日は東京へ行った幼なじみのひとり―神流夕月が帰ってくるからだ。
「かんちゃん、また帰ってきてね」
「うん、戻ってくるから大丈夫だよ」
「約束だからね」
そんな約束をして、夕月は島を出ていってしまったのを思い出す。
都会へ行った人が、星波島に戻ってくることは珍しい。戻ってくるのは冠婚葬祭か帰省が大半で、数日戻ってきたかと思うと、また島を出て行ってしまう。俺は、そうやって何人も見送ってきた。
夕月が星波島を出てからは会っていなかったから、帰って来ることは嬉しかった。むこうにいた時の土産話も楽しみのひとつだ。
都会は、テレビや新聞、クラスで「都会に行ってきたんだよ」なんて言う奴の情報が大半だ。見聞きした都会は人でごみごみしてて、どこかせわしなくて、夜になってもずっと明るいらしい。
「都会って人いっぱいいすぎ! みーんななんか忙しそうだし」
「電車に間に合わないから急いでるんだよ、なんて言うけど一本乗り過ごしても次がすぐ来るのにね」
「こっちなんでフェリーが一時間半に一本なのになぁ」
「あと都会は星なんて全然見えないなあ。見えても少しだし」
「海も全然なくて、どこ行っても潮のにおいがしない」
ここで暮らしていると海は生活の一部に溶け込んでいるし、どこにいたって潮のにおいがする。それがこの島での当たり前だ。
だからこそ、そんな東京は少し興味があるし、夕月が実際に見聞きしてきたことを聞けるのは純粋にわくわくする。
はずなのに。
心のどこかで素直に喜べない自分がいた。そんな風に思ってしまう理由も分かっていた。
(夕月があいつの初恋の相手だからだ)
夕月は小さい頃から頼りになって、兄貴みたいに俺たちを可愛がってくれた。
かっこよくて頼りになる夕月が誇らしくて、憧れで……そんな夕月に、あいつが恋をしたのは当然だと思った。
当然だと思っているはずなのに、俺の心はそう簡単に言うことを聞かなかった。
あいつに気持ちを向けられている夕月が羨ましくて仕方ない。
(今も、あいつは夕月のことを想っているんだろうか)
夕月が東京に行ってからしばらくが経つけれど、どうなんだろう。
夕月と、それからあいつの初恋を考えると胸の辺りが暗くなってくる。
自分の中に黒い感情が顔を覗かせた。
(ずるいなあ。どうして夕月なんだろう)
あいつは尊敬できる兄貴分で、かっこよくて大事な幼なじみのはずなのに――。
気が付けばため息を吐いていた。それでも、暗く重い気持ちはちっとも晴れない。
いつものように星空が見えたら、きっとこんな気持ちもすぐになくなるはずなのに。そういう日に限って、曇り空だ。
「こんなんかっこわりー……」
思わず口から出た言葉が静かな部屋に溶けていく。
早く幼なじみに会いたい。けれど、少し憂鬱。
そんなままならない気持ちに蓋をするように、目蓋を閉じた――。