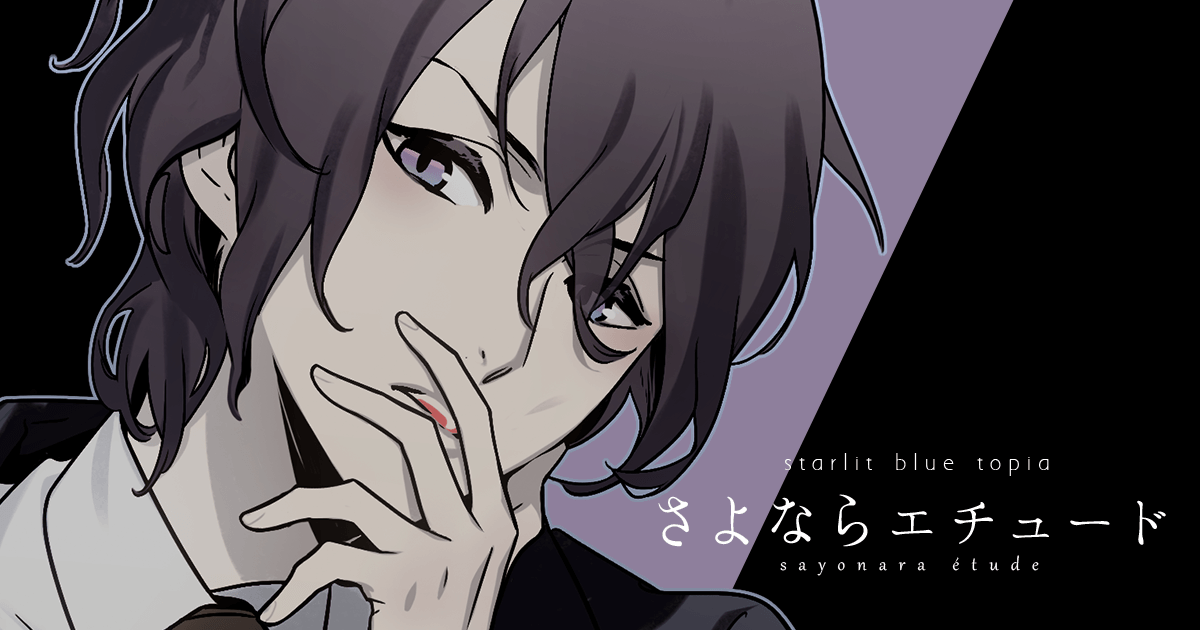Side Toa
次の楽曲の製作に入っているらしいなんてことを知ったのは、メンバーがSeekerたちと話しているときだった。
『じゃあお開きの前に、一言ずつ次の曲の目標を聞いておこうかな♡』
そんな振りをされて、僕は少なからず動揺した。
次の曲、って依空は本気で言ってるの? 僕に次はあるの?
僕はそんな言葉を飲み込んで、携帯を握り直す。画面の向こうには、依空の不敵な笑みがあるような気がした。
次の曲の話は、恐らく僕が家の用事でいないときにされていたんだろう。けれどそれは当然のことだった。
僕は四月からはこのバンドのサポートを辞めなければいけない。そもそもサポートに入ったのだって、期間限定の、という条件付きだった。
僕が鈴音叶亜として生まれてきたのだから、これは仕方のないことなのだ。
「これが、俺たちの出した答えだ。やりたいなら、レコーディングに来い。後はお前が選べ。それが、お前の答えだと思ってる」
そんな勝手な言葉と共に、依空に渡されたのは新曲のデモだった。
僕の前には一本の道しか残されていないことを知っていて、依空はこの言葉を選んでいるに違いなかった。
そして依空からそれ以外の言葉がなかったのは、きっと聞けば分かるから、ということなんだろう。あんなにお喋りな依空も、結局のところ本当に知って欲しいことは音楽でしか語ってくれない。
僕はいてもたってもいられなくなり、依空から貰ったデータを携帯で開いた。
再生ボタンをタップして流れて来たのは、まとまりのない、けれどどこまでも自由な音たち。僕が欲しくて欲しくてたまらないものたちだ。
五分足らずのそれに、彼らの本気と覚悟の全てが詰め込まれているのが分かって、ただただ茫然とした。
僕はこれを手放さないといけないのか。こんなにも鮮やかで、苛烈なこれに目を瞑らないといけないのか。
そう思うと、笑えるくらい泣けてくる。じわりと目頭が熱くなってきて、喉の奥がきゅっと閉まる。こみ上げてくるものを誤魔化すように、目を瞑って深く息を吐いた。涙は落ちては来ない。
心残りが無い訳なんてない。今だって僕は彼らの全てを知っている訳ではないけれど、彼らと音を紡いでいくのは楽しかったし、音楽に向ける想いは本物だということを知っていた。
できるならもっともっと、続けていきたいと思っていた、けれど。
それでも、やっぱりけじめはちゃんとつけなくちゃいけない。僕にはもう時間は残されていなかった。
シンデレラは夜の十二時に魔法が溶けるように、魔法使いがかけた夢はいつか覚めるから夢なんだ。覚めない夢は、きっと夢なんて呼ばない。
「……ごめんね」
心に決まったその言葉を告げるために、僕は依空に電話した。
Side Isora
傍から見れば、恐らくこれは勝率の低い賭けだった。いや、賭けにすらなっていないかも知れない。
くるくると盤上を回っているボールは、俺がゲームを始めた時から「叶亜が抜ける」というホールに落ちることが決まっている。それでも俺は、この勝負に全てをベットしていた。
三月、叶亜以外のメンバーと新曲の打ち合わせをしたとき、新曲には当たり前のようにキーボードの音が組み込まれていた。俺が有貴に、そういうオーダーをしたからだった。
「次の曲はピアノ入れて欲しいな~」
「……分かったよ」
分かったと言いつつも、有貴はじろりと俺を見て呆れたように息を吐いた。
「依空は人が悪いね」
「そんなつもりはないんだけどな」
「どうだか」
有貴は了承し、ピアノを曲に入れることについては何も聞かなかった。分かっているからあいつは何も聞かなかったのだ。
期間限定でもいいからと半ば無理やり叶亜をキーボードに入れたのはいくつか理由があった。
キーボードがあれば曲として完成度が上がるからというのが一番だったが、叶亜がキーボード以外の楽器にも精通しているのも大きかった。そして、聞けば弟の亜蘭もピアノが弾けるのだという。もっとも、弟の方はもっぱらギターばかりだと言うが。
いつものように叶亜の弟語りを話半分に聞いていたが、これを知ったときばかりは、俺は内心ガッツポーズをした。
なぜって? 『期間限定』以降も、キーボードを使った曲が作れると思ったからだ。
そして叶亜不在の打合せで有貴から上がって来た音源を聞いた亜蘭は、ことさら機嫌が悪かった。
みんなでPCの音に耳を澄ませていると、亜蘭が不意に声を上げる。
「おい、ちょっと待てよ」
「ん、どうしたー?」
「……キーボード、どうすんだよ」
「あーキーボードな。SUZUNEっつったらグランドピアノだろ? 亜蘭もそこの息子ならピアノ弾けるんだろ?」
「オレはギターを弾くためにここにいるんだよ。キーボード弾くためじゃねえ」
亜蘭のことだ、そこはオレの場所じゃないとでも言いたいんだろう。そうだよな、そこは本当はお前の場所じゃない。
「でも弾くやつが他にいないんだからしょうがない。できる奴ができることをやる、それが当然だろ?」
不機嫌そうに眉を寄せる亜蘭だったが、それからとどめの一言。
「叶亜にお前の熱意を見せれば、叶亜だってきっと考え直すんじゃないか?」
「……クソ!」
そんな言葉と共に、亜蘭は会議室の席から乱暴に立ち上がる。亜蘭の苛立ちの原因は、叶亜か、自分か、それから俺か――。恐らく全部だろう。
「おーい亜蘭、まだ会議は途中だろ~?」
「休憩」
目を合わさないまま短く吐き捨て、会議室を出ていった亜蘭の背中を見送る。亜蘭のそんな行動も想定の範囲内だった。
この賭けが一体どうなるのかは俺自身にも分からなかった。それでも、あいつをこのゲームから降りることはさせない。勝ち逃げなんて、俺がさせると思っているんだろうか。答えは否だ。
俺は俺の勝ちのために、俺のできることをし続けるだけだ。くるくると回っていたボールがホールに落ちるその瞬間まで。